 鎮座地(河内国丹南郡日置荘について!)
鎮座地(河内国丹南郡日置荘について!) 河内平野
当地は金剛山系の山々より発する天野川の流域に、六世紀末頃造られた狭山池より西除川を利用した稲作が古くより行われ、付近には古墳時代の窯跡や奈良平安時代の住居跡などの遺跡も発掘されている。
荘園制をうかがう
尚 日本書紀に出てくる古道の「茅渟道」は、竹内峠より富田林喜志を通り 平尾、黒山から当地の日置荘、関茶屋を経て和泉に至る道と推定されており 一部に条理制のうかがえる地割が最近まで日置荘北町付近にあったが、その東西線が重要な役割を果たした茅渟道の一部とも考えられる。
日置部について
また日置の地名より古代の太陽祭祀に関係する「日置部」の支配した土地であったとも云われているが、これを受け継ぐかのように時代は全く下がるものの、日置西村に日祠宮があったことが江戸後期の「河内名所図絵」に記されている、これは現在古老が「バンジサン」と言っている「三十番神」のことであるのでいつの頃か太陽信仰と習合したものと思わ れる。
830年前の古文書に
鎮座地の日置荘は平安末期、承安四年(一一七四)の吉記と称す日記に、興福寺領 河内國狭山郷内日置庄と見えるが、この記録に日置庄が河内国司より造内裏役を課せられたがその税を納めなかったのは、当地の住人が、蔵人所の灯楼の作手のために、課税を免除されているからであると云う内容が記されている
河内鋳物師
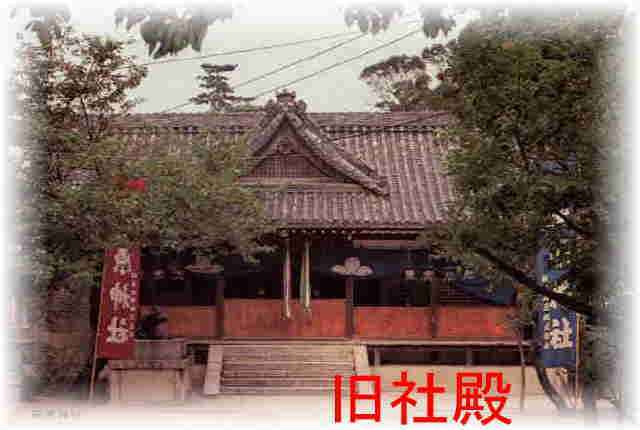 又 ある文書に「右方鋳物師者、日置、金田、長曽禰此三ヶ所也」 この書から 丹南郡日置荘が、鋳物師の住まいする土地であったことが解されるし、最近では付近の発掘調査で鋳物に
関する遺物がいろいろと発見されている 又近世物であるが各地に「河内国云云」と刻された鋳物製品が文化財として遺っている。
又 ある文書に「右方鋳物師者、日置、金田、長曽禰此三ヶ所也」 この書から 丹南郡日置荘が、鋳物師の住まいする土地であったことが解されるし、最近では付近の発掘調査で鋳物に
関する遺物がいろいろと発見されている 又近世物であるが各地に「河内国云云」と刻された鋳物製品が文化財として遺っている。
日置荘
尚 日置荘は荘園の名残の地名であるが、荘園は中古以来各地に発生してこの付近も野田荘、丹比荘、毛受荘、陶器荘などがあり公領の他は、ほぼ公家、寺社領などの荘園となっていたが鎌倉末期から、武士の発生により大豪や有力名主の力の増大により南北朝には各地の荘園は崩壊した。しかし当日置荘は南北朝の混乱の中、比較的おそく室町期まで荘園として続いたようである。
日置氏(吉村氏)
日置西村の江戸時代の大庄屋は、日置の姓を名乗っていた吉村氏である。さらに吉村氏は、和泉の伏屋家を始め島泉(現在羽曳野市)の吉村家などと姻戚関係にあった。吉村五郎右衛門正近は元禄ころに和泉の伏屋家から養子にきて、関茶屋新田開発などに活躍しているが、これらの開発は伏屋家の影響が大きいようである。
西町の日置里と刻まれた、上の灯籠の写真は文政ころに日置正美が建造したものである。碑文には「曇りなき君が御代には茜さす 日置里は賑わいにけり」と刻まれる。
尚 この伏屋家.吉村家(日置)は文人が多くでていて、延享4年生まれで伏屋家に養子となり分家を再建した伏屋素狄(そてき)は日本実験生理学の開祖と云われているが、解体新書を著した杉田玄白と同時代の人で、優れた蘭学医師で特に腎臓に詳しく、彼の研究した資料が、伏屋家の親戚になる富田林の神社の青谷家に残されている。
◎トップページ ◎泣き相撲 ◎天神さまについて ◎秋祭り ◎神社神道
◎ローカルリンク ◎神社関係リンク ◎神職と役員の紹介
お問い合わせはこちらに(萩原神社社務所行き) にお願いします